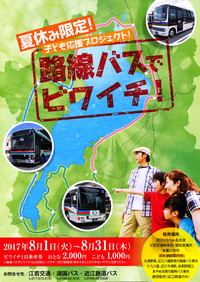2008年12月06日
穴太(あのう)の石積み
穴太(あのう)積みの石垣を見たくて但馬の竹田城を訪ねる。(2008.12.5)
 1.竹田城(1)
1.竹田城(1)
但馬竹田城跡はJR播但線竹田駅のすぐ西側にある古城山(353m)の頂上にある。
現在、建物は全く残っておらず、石垣のみが山上に残されている。穴太積みの城郭の石垣としては日本一美しいと絶賛され、急峻な山上の尾根に築かれたその姿は「日本のマチュピチュ」とも呼ばれている。
 2.竹田城(2)
2.竹田城(2)
穴太積みとは坂本の隣り、穴太(あのう)に伝わる石工集団である穴太衆(あのうしゅう)による石積みをいう。
穴太衆は、古くは横穴式古墳の石室造りに習熟していた渡来人の子孫であろうといわれている。その後、比叡山延暦寺の多くの堂宇を建てるために山の斜面に平地を確保するための石積みを担ってきたいわば延暦寺の営繕部門を担当してきた。
 3.竹田城(3)
3.竹田城(3)
穴太積みの石垣は専ら大小の自然石で積み上げられている。奥行きのある自然石で積むため非常に強固で地震にも強く、見た目にも美しい。そのため全国の城の石垣のほとんどはこの穴太積みで築かれている。滋賀県では安土城、彦根城、観音寺城、宇佐山城等。その他、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に釜山を中心に乱立して築かれた倭城(わじょう)の多くも穴太積みであったという。
 4.竹田城(4)
4.竹田城(4)
竹田城跡から見下ろす竹田の町並み。
 5.坂本・里坊(さとぼう)
5.坂本・里坊(さとぼう)
坂本には延暦寺で修行を終えた老僧の隠居寺である里坊が約40ヵ寺もある。いづれも自然の渓流を利用した清閑な庭園や穴太積みの石垣を配しており、坂と石垣の美しい町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区(略して伝建地区)に指定されている。
 6.坂本・滋賀院
6.坂本・滋賀院
坂本の中でも滋賀院門跡の石垣は見事である。
 7.滋賀院の穴太積み
7.滋賀院の穴太積み
滋賀院門跡の穴太積み詳細。
 8.大津市歴史博物館の穴太積み
8.大津市歴史博物館の穴太積み
穴太積みの石垣はデザイン的に現代建築ともよくマッチするので、大津市歴史博物館のアプローチの石垣や滋賀県立大学キャンパスの修景にも効果的に採り入れられている。
安土城から400年を経たいまなお、穴太衆のメッカ、近江坂本に全国で唯一穴太積みの伝統を保持する家系が存在する。現在15代目を数える粟田家である。
 1.竹田城(1)
1.竹田城(1)但馬竹田城跡はJR播但線竹田駅のすぐ西側にある古城山(353m)の頂上にある。
現在、建物は全く残っておらず、石垣のみが山上に残されている。穴太積みの城郭の石垣としては日本一美しいと絶賛され、急峻な山上の尾根に築かれたその姿は「日本のマチュピチュ」とも呼ばれている。
 2.竹田城(2)
2.竹田城(2)穴太積みとは坂本の隣り、穴太(あのう)に伝わる石工集団である穴太衆(あのうしゅう)による石積みをいう。
穴太衆は、古くは横穴式古墳の石室造りに習熟していた渡来人の子孫であろうといわれている。その後、比叡山延暦寺の多くの堂宇を建てるために山の斜面に平地を確保するための石積みを担ってきたいわば延暦寺の営繕部門を担当してきた。
 3.竹田城(3)
3.竹田城(3)穴太積みの石垣は専ら大小の自然石で積み上げられている。奥行きのある自然石で積むため非常に強固で地震にも強く、見た目にも美しい。そのため全国の城の石垣のほとんどはこの穴太積みで築かれている。滋賀県では安土城、彦根城、観音寺城、宇佐山城等。その他、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に釜山を中心に乱立して築かれた倭城(わじょう)の多くも穴太積みであったという。
 4.竹田城(4)
4.竹田城(4)竹田城跡から見下ろす竹田の町並み。
 5.坂本・里坊(さとぼう)
5.坂本・里坊(さとぼう)坂本には延暦寺で修行を終えた老僧の隠居寺である里坊が約40ヵ寺もある。いづれも自然の渓流を利用した清閑な庭園や穴太積みの石垣を配しており、坂と石垣の美しい町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区(略して伝建地区)に指定されている。
 6.坂本・滋賀院
6.坂本・滋賀院坂本の中でも滋賀院門跡の石垣は見事である。
 7.滋賀院の穴太積み
7.滋賀院の穴太積み滋賀院門跡の穴太積み詳細。
 8.大津市歴史博物館の穴太積み
8.大津市歴史博物館の穴太積み穴太積みの石垣はデザイン的に現代建築ともよくマッチするので、大津市歴史博物館のアプローチの石垣や滋賀県立大学キャンパスの修景にも効果的に採り入れられている。
安土城から400年を経たいまなお、穴太衆のメッカ、近江坂本に全国で唯一穴太積みの伝統を保持する家系が存在する。現在15代目を数える粟田家である。
Posted by ミッチー at 10:42│Comments(0)
│滋賀の風景